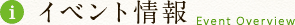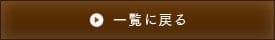最新ニュース
-
お知らせ2026/01/21
大野山山頂公衆トイレについて
-
お知らせ2026/01/08
町立中川温泉ぶなの湯「臨時休館」のお知らせ
-
お知らせ2026/01/07
町立中川温泉ぶなの湯「臨時休館」のお知らせ
-
お知らせ2025/12/24
町立中川温泉ぶなの湯「臨時休館」のお知らせ
-
お知らせ2025/12/13
ユーシン渓谷へ続く道の通行について
-
お知らせ2025/11/25
冬季(12月~2月)開館時間変更及び年末年始の休館...
-
お知らせ2025/11/25
ぶなの湯冬期営業のご案内
-
お知らせ2025/11/23
丹沢湖マラソン大会開催に伴う交通規制のお知らせ
-
自然情報2025/11/14
紅葉が見ごろを迎えています!(11月14日撮影)
-
お知らせ2025/11/07
ハイキング・登山に来られる方へ【クマにご注意くださ...
- 山北町観光協会TOP
- イベント
- 室生神社の流鏑馬(県指定無形民俗文化財)
室生神社の流鏑馬(県指定無形民俗文化財) 2025年本イベントは終了しました。

その思いで、室生神社流鏑馬保存会がクラウドファンディングを始めました!
ご支援は下記リンク先の、「室生神社の流鏑馬」のクラウドファンディング公式ホームページに
アクセスして実施いただきますようお願いします。



神奈川県指定無形民俗文化財「室生神社の流鏑馬(むろうじんじゃのやぶさめ)」は毎年11月3日の室生神社の例大祭に神事として古儀に基づき行われています。
山北町山北の宮地に所在する室生神社に伝わるもので、起源は源頼朝の石橋山挙兵の際、平家方に味方したため領地を没収され、斬刑に処されるところであった河村義秀(かわむらよしひで)が、鎌倉で行われた流鏑馬の妙技により刑を免ぜられ、旧領に復帰できたという故事(『新編相模国風土記稿』『吾妻鑑』)によるとされています。故事では鎌倉で流鏑馬が行われたのは建久元年(1190年)なので、義秀が旧領に復帰した翌年から「室生神社の流鏑馬」が始まったとすれば、現在まで約800年余り続いていることになります。
農家の人々により受け継がれていた時期もあり、かつては的の当たり矢によって翌年の稲作を占う神事としても行われました。三つの的は、一の的が早稲、二の的が中稲、三の的が晩稲のできをあらわしました。

流鏑馬神事は「馬場駈け」「流鏑馬開始の式」「馬場入りの儀」「垢離取り(こりとり)の儀」「流鏑馬始式」「騎射」の順に執り行われ、拝殿前の「終了報告」をもって終了となります。
「馬場駈け」は騎乗者がハッピ姿で裸馬に乗り、2頭で馬場を一往復します。
「流鏑馬開始の式」では騎乗者は正装に着替え騎乗し、神社拝殿前で神官によるお祓いを受けます。

「馬場入りの儀」では流鏑馬神事関係者が行列を組み、拝殿東側から神殿の裏を通って馬場入りをし、垢離取場へ向かいます。
「垢離取りの儀」は旧皆瀬川の岸辺にあたる山北町山北の字金森に所在する垢離取場で行われます。中央の御幣を右回りに3周し、馬の足と口を浄めます。その後再び神社に戻ります。

「流鏑馬始式」では一の的を鳥居前の馬場中央に社殿を向けて立て、騎乗して的を左回りに3周した後に騎射し、それと同時に前方に待機したもう1頭(先馬)が馬場尻へ走り出し、後馬が続き、二の的、三の的を騎射します。




※午前中は花車や神輿が山北地区を回ります。